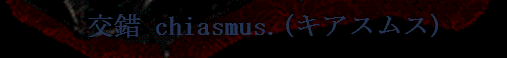作者:崋山宏光へメールする!
同じ頃澪は貧しい仮住まいの東屋の薄ぺらな布団の上に座ったままで眠れぬ夜を過ごし夜が白んでくるのを知らずにいた。長い時間ひとりぽっちでまんじりともせずに尚三との思い出に浸っていた。澪にとって尚三は白馬に乗った王子であった。その想いは紛れもなく疑う余地は無かった。澪が両親の痴話喧嘩にはじかれて外でひとり侘しい時を潰していた時に澪の前に突然訝しく眉を狭めて澪の前に現れて澪を見つめ「一緒に遊ぼう!」と言ってくれた。その時の尚三はきっととても緊張していてあんなに訝しげな顔立ちになったのだと思い出して澪はひとり思い出し笑いに耽った。尚三の笑顔は澪のかけがえの無い思い出だ。心の底から搾り出すように眩しい笑顔を見せてくれた。澪は今でも尚三が大好きだった。大好きだから離れる決心ができたのだと思った。
このまま豊かさに甘んじて見過ごしていては尚三の人生が壊れてしまいそうで堪えられなかった。貧しくてもいい尚三に昔の心を取り戻して欲しかった。尚三はやさしさが眩しい程心が純な男気に覆われていた子供であったことが唯一澪の大切な人生の支えだったのっだから。そんな尚三が澪を幸せにする事に夢中になって自分の目を曇らせていることに気付かないのが澪はくやしかった。澪が愛した尚三と言う男は金に目をくらませて善悪を取り違えるような男ではないと知っていた。自分が尚三の側を離れることで尚三はきっと自問自答して過ちを自分自身で糺す事ができると信じていた。
だから尚三のもとを離れて暮らすことはこのうえなく辛かったがその辛さを犠牲にしても尚三に思い直す機会を与えてあげたいと思った。澪は何年でも待つつもりだった。尚三はきっと昔の尚三に立ち戻って昔のあの天真爛漫な笑顔で再び澪の前に現れ微笑んで連れ戻ってくれる。病に冒された澪の体がそれまで持ち堪えられるかどうかは分らないがそれはその時の運命次第と思い切って居られた。死んだ跡から気付いてもそれはそれで充分だと納得した。今まで幸せを培ってくれたのは間違いなく尚三の今までの生き様なんだと。もうここまででも充分すぎる幸せな日々があった。ただ赦せないことは赦せないこととしてけじめを付けて死を迎えたいと望んでいた。
澪の体は弱りきっていた母として妻として女としてひとりの人間として精一杯生き抜いてきて疲れ果てていた。激動の時代の荒波はひとりの家庭を守る女にさえ激しき飛沫をあげて覆いかぶさり呑み込んで過ぎ去った。その荒波の何奇跡的に命を残され生きられたようなものであった。生きているということだけでありがたいと思えるくらいの激しい嵐の時代を生き抜いて来た。だから思い起こせば平和な幸せだけが蘇える訳はなかった。幸せのほうが心の記憶の大半の部分を占めてはいたがそれは不幸に蓋を被せて生きてきただけのことだ。心に残っている総てがそうではなかった事を長い宵の闇の中でひとつひとつ思い起こしていた。辛かったこと悲しかったこと切なかったこと侘しくてどうしょうも無い時につまらなく女の性をさらけ出した事などあらためて自分と向き合いもうひとりの澪が今までの澪の生き様を見つめ直していた。思い起こした過去の記憶を反芻するようにあげ戻し噛み砕き再び自分の胸の奥底へ仕舞込んだ。そうして過去を掘り起こして見ても過ぎ去った過去は過去でしかなく楽しみも悲しみも二度と同じ感慨を味わうことなどできないしましてややり直すことなど不可能であった。人生?辛いけど楽しかった・・・。澪はそう思った。そうして一夜が過ぎた。
澪は板戸の隙間から淡い薄日が差し込んでくるのを知った。僅かな隙間から差し込む光は闇を裂き輝いていた。その光の中に陽炎のよう立ち上る朝靄を感じてそのやわらかな陽光に微笑みを取り戻して布団の上から立ち上がって板戸をあけた。
東の峰に顔を覗かせつつある朝日の輝きを目にした澪は右手を翳して左手で袂を押さえつつ微笑み見ながらご来光を拝した。眩しかった。澪の顔が朝焼けに輝く。澪はその眩しさがいわれなく嬉しくて微笑を深めて歯を見せて笑顔が蘇えった。清清しさが溢れて澪を幸福感が支配した。束の間澪は一人ぼっちを忘れた。徹夜の疲れが一変に吹っ飛び明るい兆しが朝の輝きとともに訪れてくる気配を感じずには居られないほどになった。しばし朝日の創る荘厳な朝焼けを堪能してすべての悲しみをその輝きで消してしまいたいと願った。はたして神は澪の願いを聞きとどけてくれるのだろうか。それは神のみぞ知ることである。
つづく・・・。
Upcoming changes to FeedBurner
-
FeedBurner has been a part of Google for almost 14 years, and we're making
several upcoming changes to support the product's next chapter. If you use
FeedB...
3 年前